お知らせ・活動報告
2025.07.26 (Sat) 11:00
帰農学校vol.14
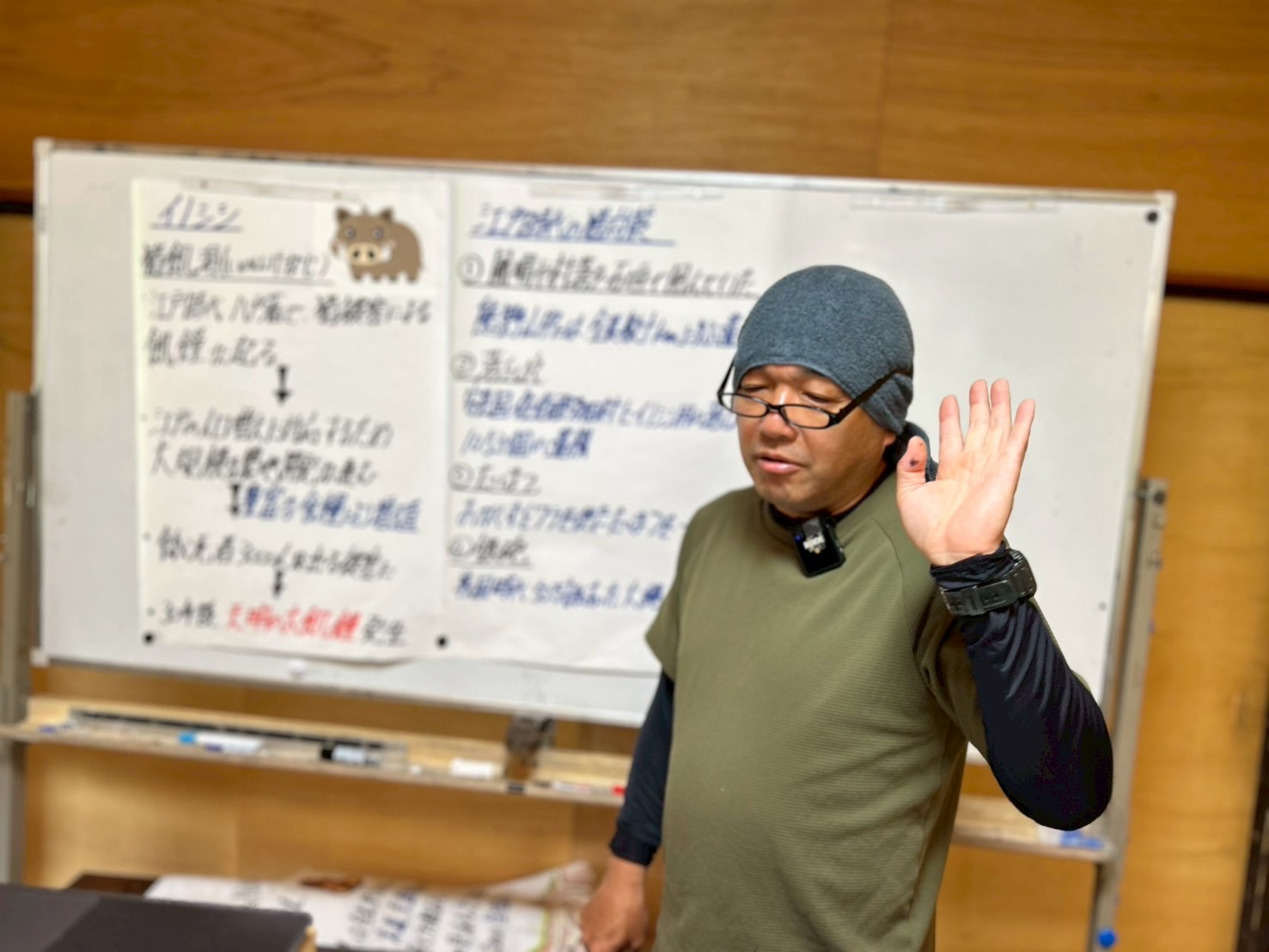
鳥獣被害について
人類が農耕を本格的に始めて約6000年
未だ解決されない問題が『鳥獣被害』
彼らが元いた場所にニンゲンが進出し
田畠を作り 道を敷き 川の流れを変え
昨今では農薬 除草剤に住処を奪われ
生きる為に里におりれば殺される。
彼らにすれば、『人間被害』となるのであろう。
江戸時代 八戸藩(青森県八戸市周辺)において
3000人もの人が餓死するという『猪飢渇(いのししけがじ)』という飢饉が起こった。
そのきっかけは、江戸時代中期、江戸や大坂などの都市で人口が増大し、食生活に不可欠だった味噌の原料である大豆が大量に必要とされた。
しかし、開田政策によって都市近郊では大豆を作れる農地がなくなっていたため、幕府は東北の諸藩に
大豆栽培を奨励し八戸藩もその方針に従い大規模な
農地開発を行なった。
当時の農地は、山野の草木をきり払い、火入れをして焼畑をつくり、雑穀類を二、三年栽培したあとは休耕する。
焼畑あとには一年生雑草、そしてワラビやクズ、ススキの多年草が入り込み、やがてナラなどの木が育つ。
こうして二〇~三〇年経つと再び焼畑の適地になる。
よって一定面積の焼畑を経営するためには、その二〇~三〇倍の面積が必要であった。
そこに大豆の生産が加わり、休耕地にワラビ、クズ、ススキが増植。
これらの植物性食料を餌にする大型の動物はイノシシのほかにはなく、こうして豊富な食料を独占できたイノシシが異常に繁殖するようになり、ついには耕地を荒廃させ作物を荒し、さらにはそのために多数の餓死者を出すに到ったのである。
これが、猪飢渇(いのししけがじ)の実態である。
それから30年後 天明の大飢饉が起こり、更に多くの餓死者が出る事となる。
ただこれは300年前の出来事ではすまされない
事情を含んでいる。
戦後日本は、農本主義から資本主義の世となり、さらに食の欧米化が進み、米余り現象の中、1971年より減反政策がはじまった。
この減反政策により日本各地に耕作放棄地が出現し
かつての八戸藩開田政策による休耕地と同様ワラビ、クズ、ススキ、そして新たにセイタカアワダチソウが加わり、イノシシにとってかっこうの繁殖地となった。
それらが次第に増殖、田畠に侵入し、作物を荒すに至る。
このまま何の対策も講じず耕作放棄地を増やし続ければ、『令和の猪飢渇』が起こりかねない。
今こそ江戸時代の教訓を生かし、日本農業を建て直す時ではないだろうか。
現在しきりに里にあらわれる熊、イノシシ、シカ、サルなどはそれを我々に教えてくれているのかもしれない。
2025.07.13 (Sun) 11:02
帰農学校vol.13(特別回)

